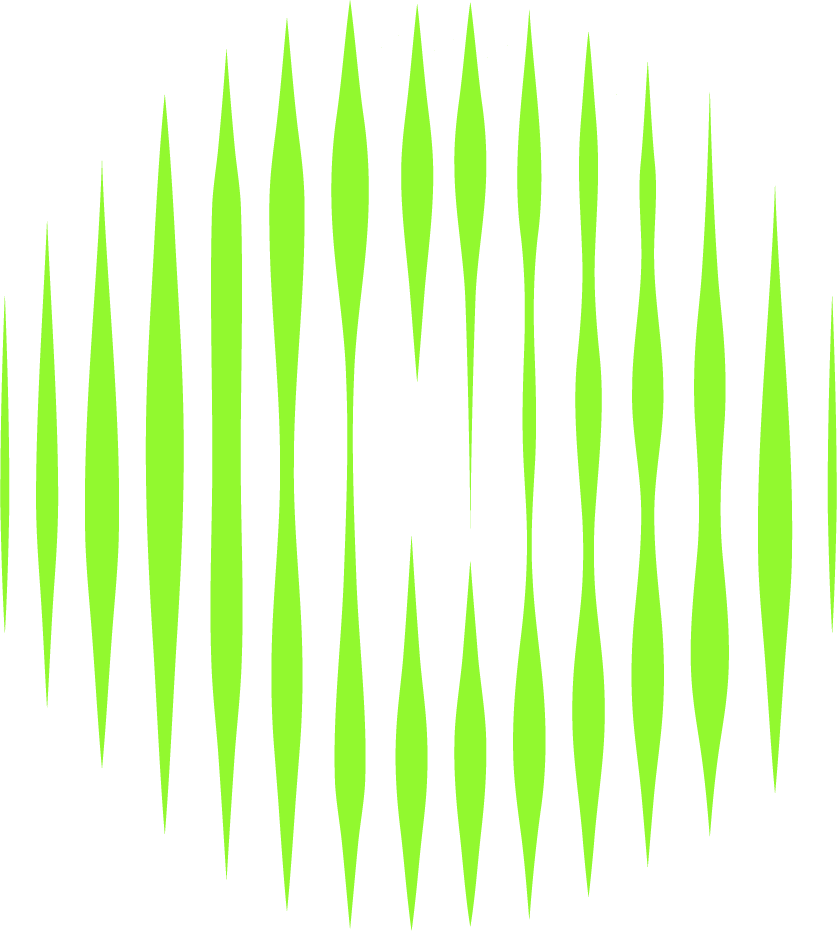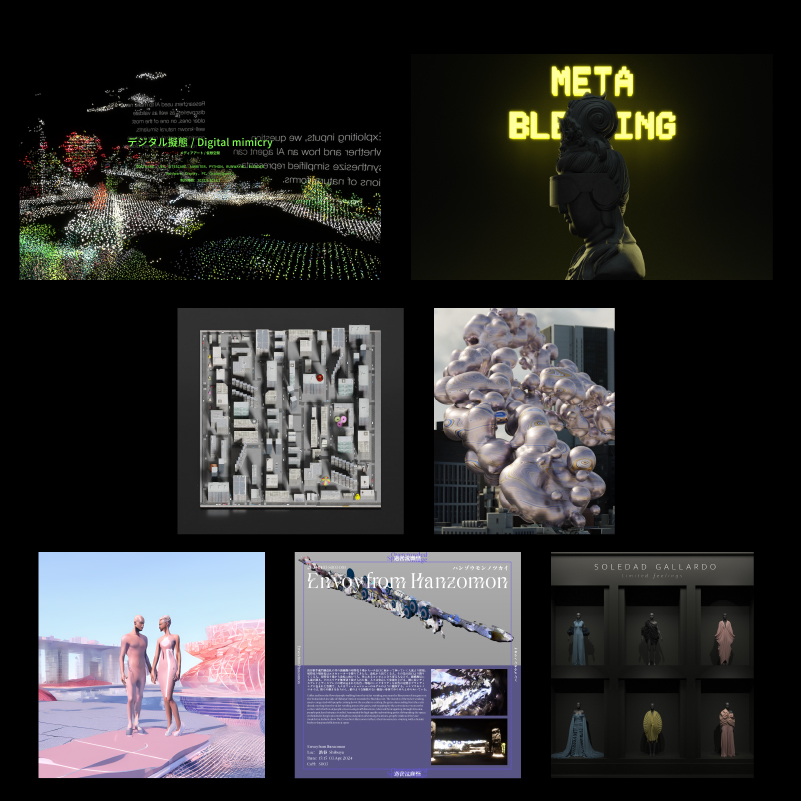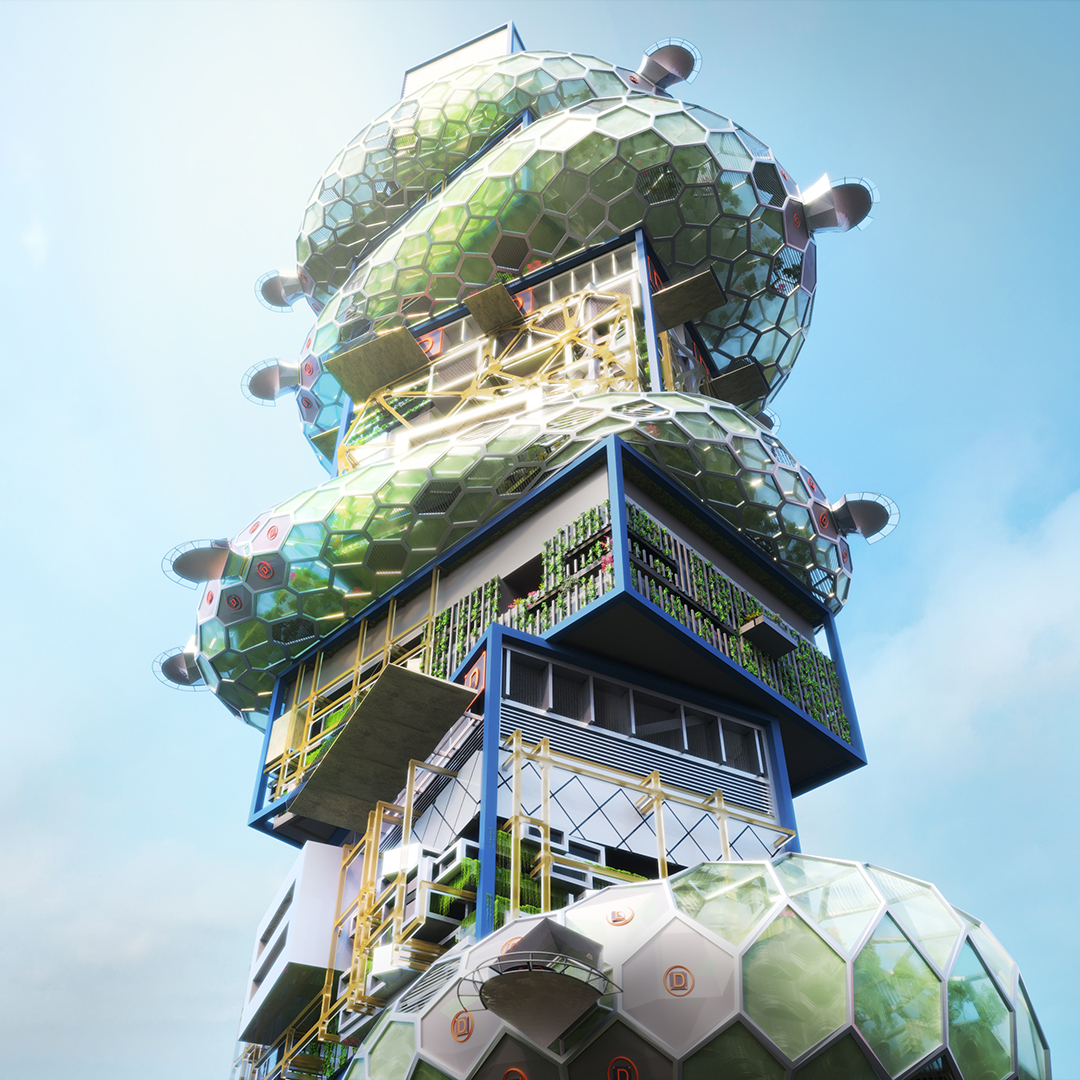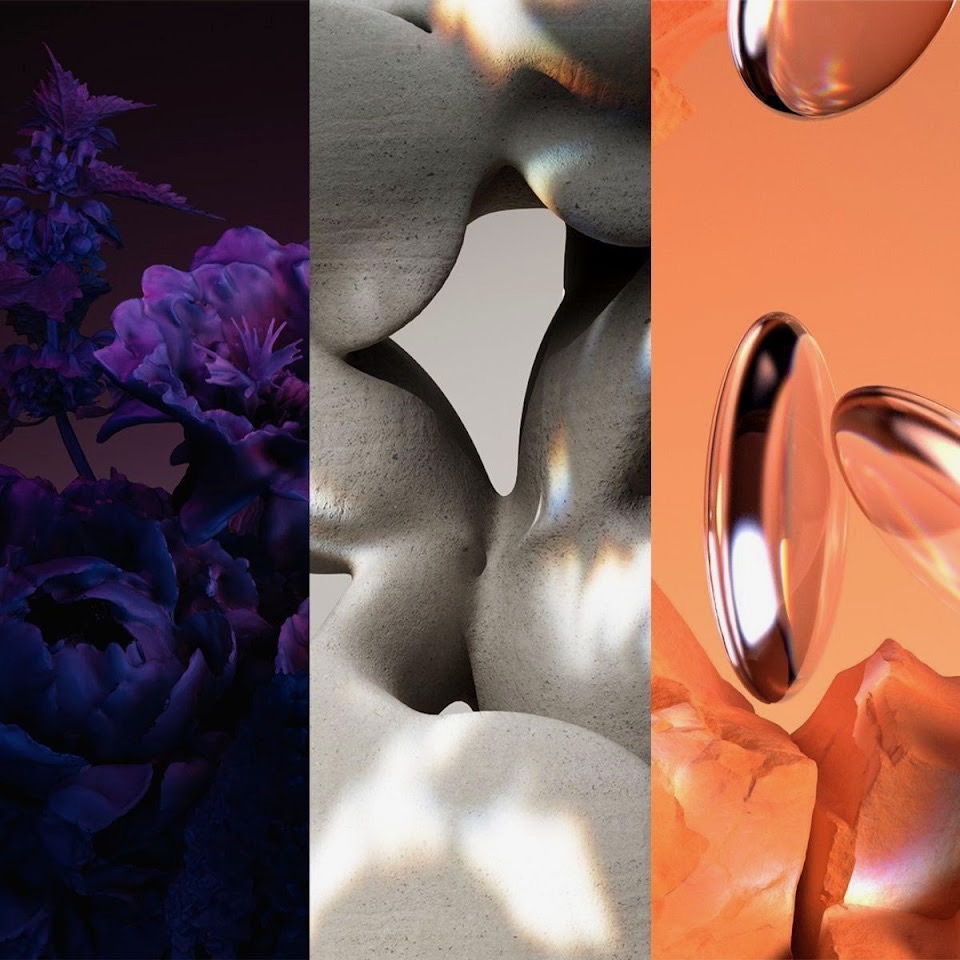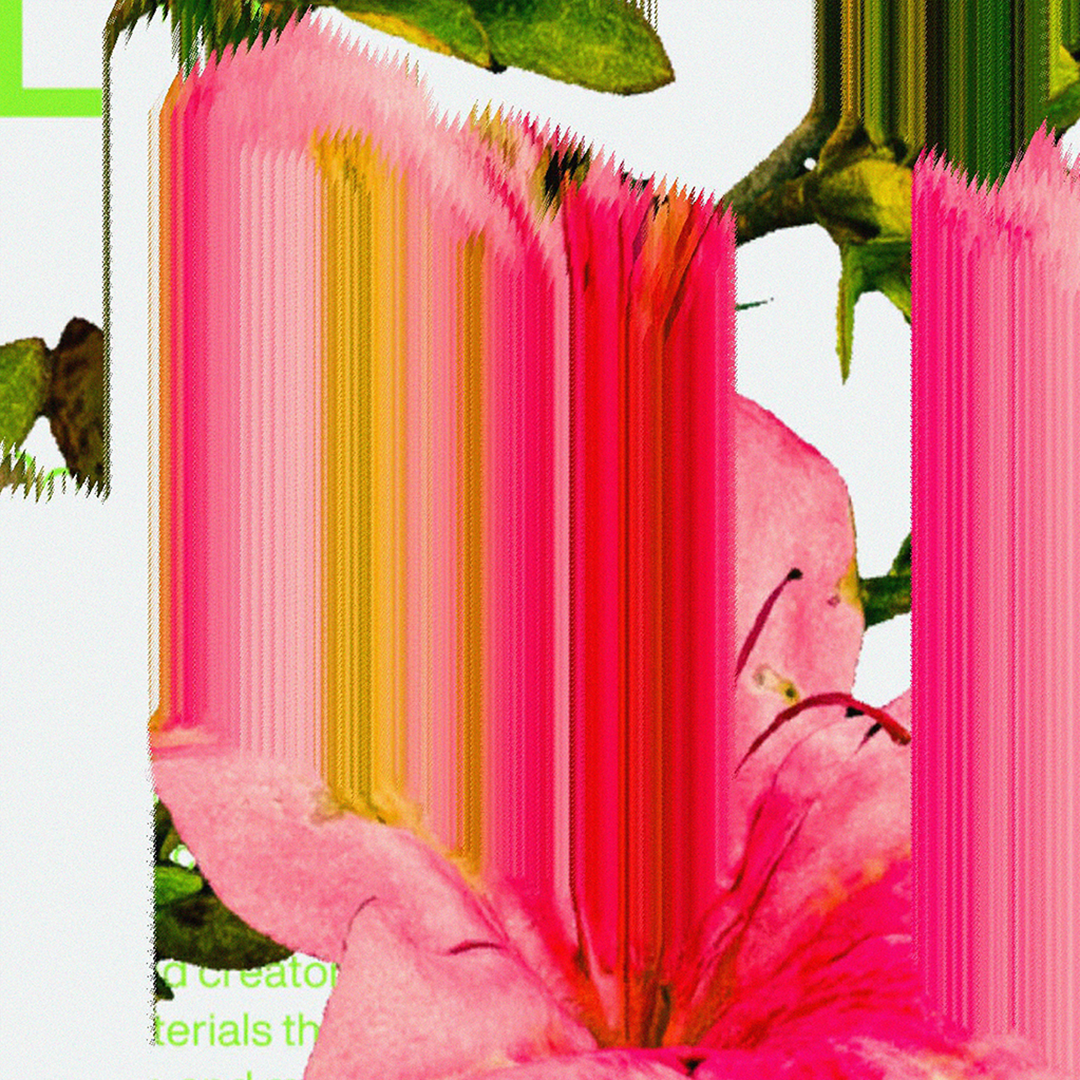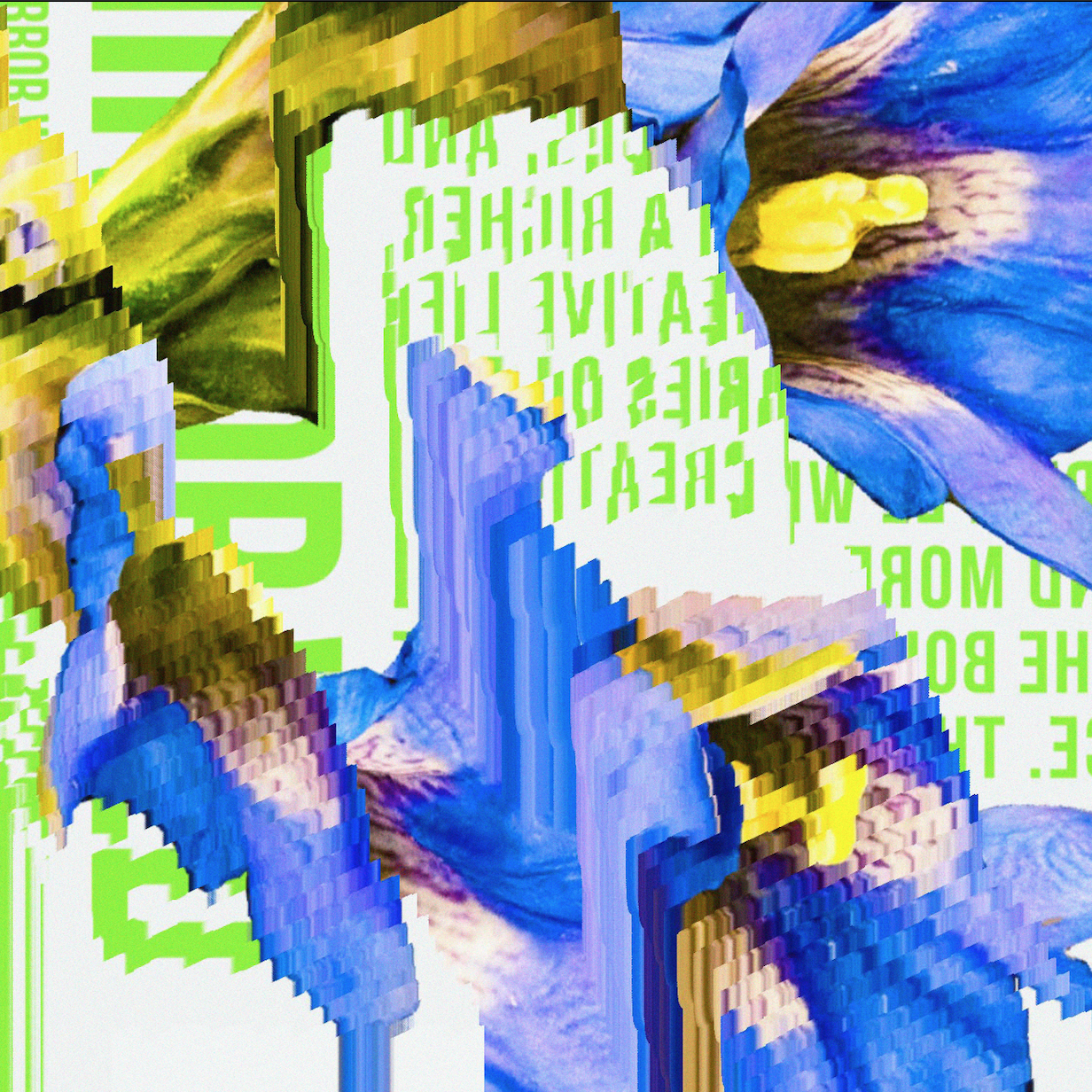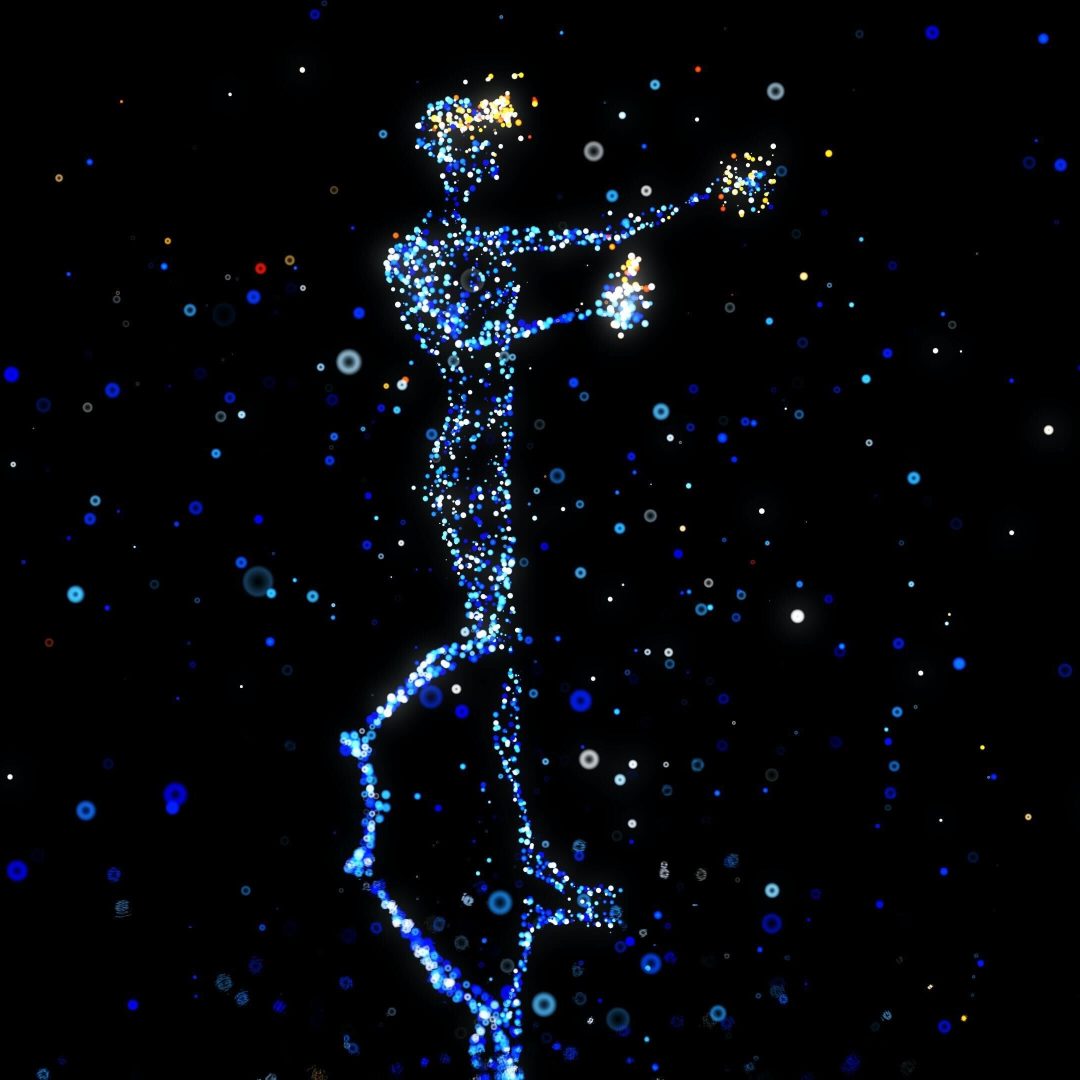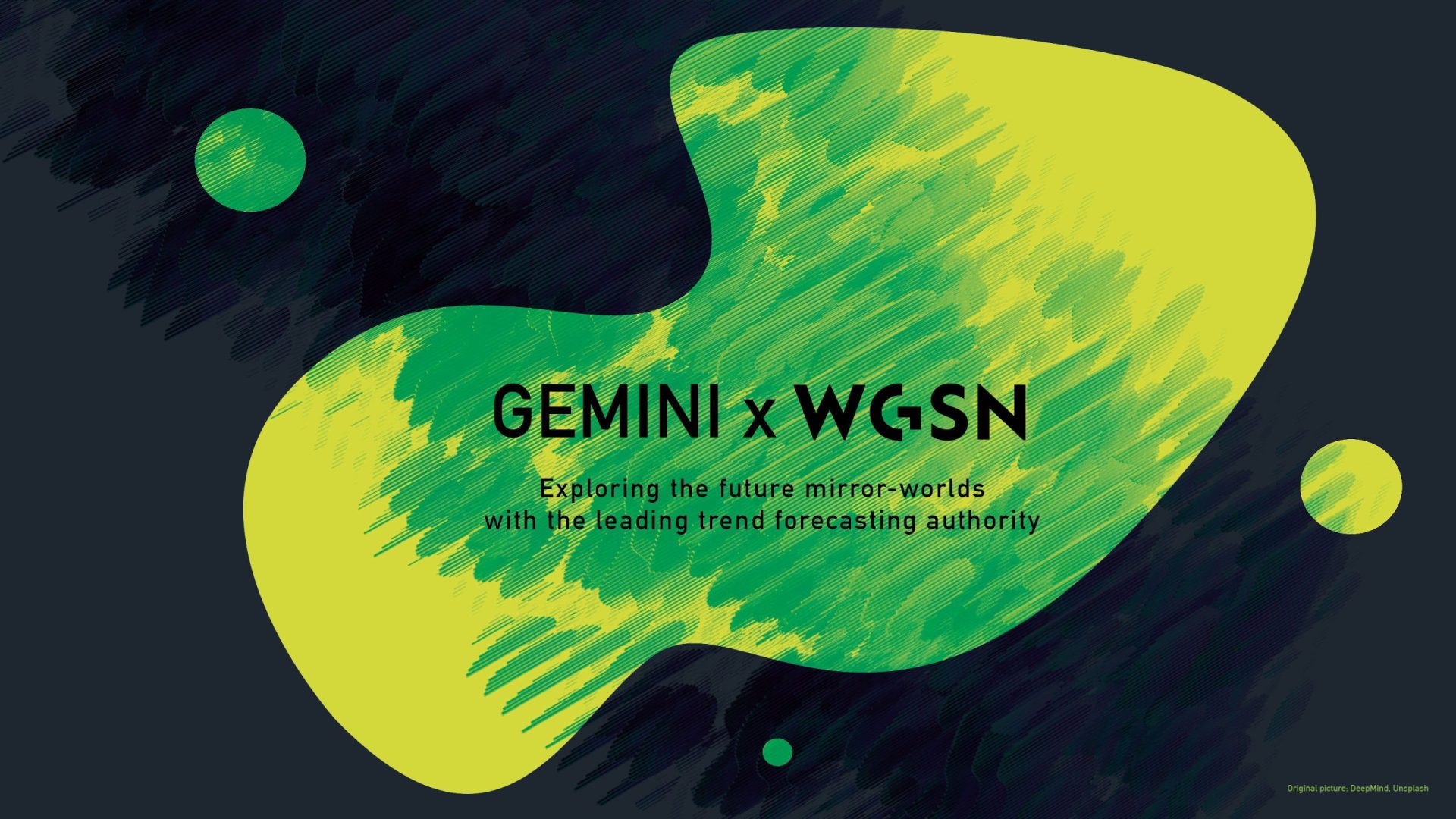これまで歌舞伎町や道頓堀などをモチーフに、リアルな繁華街の街並みを再現してきたセガの人気ゲーム「龍が如く」シリーズ。最新作『龍が如く8』では、舞台をハワイに広げ、熱い男たちの生きざまを描く。
街並みの再現性の高さからも、人気を集めてきた同シリーズだが、開発統括する龍が如くスタジオ代表の横山昌義は「じつはリアルなものをつくりたいという欲望や発想はない」と話す。その理由は?
『龍が如く8』ストーリートレーラー
「ゲームに飽いた大人たちへ」が出発点
―「龍が如く」シリーズでは、歌舞伎町をモチーフにした架空の繁華街「神室町」を中心に、精巧につくられた現代の都市空間が描かれてきました。最新作『龍が如く8』(以下、8)では、シリーズ初となるハワイが登場しています。作品を重ねるごとに技術を進化させてきた同シリーズですが、そもそもの出発点はなんだったのでしょうか?
横山:出発は「大人が楽しめるゲームが世の中にないよね」というピュアな疑問からでした。ゲームは玩具の延長線上にあってキッズのものという固定観念があったけれど、時代が進むにつれ、子どものころからゲームをやっていた人間が大人になってもゲームで遊ぶようになってきていました。
音楽であればビートルズもサザンオールスターズもずっと聴いていられるけれど、ゲームからそういった作品はまだ生まれていなかった。ゲームをやりたくても、童心に帰ってプレイしなきゃいけなかったんです。だとすれば、ゲームは今後どう発展していくんだろうと考え、浮かんだのが「ゲームに飽いた大人たちへ」というキーワードでした。

セガ「龍が如くスタジオ」代表・制作総指揮。セガ執行役員。1999年、セガにプランナーとして入社。「龍が如く」シリーズ初期作からシナリオ・演出を担当。2010年からシリーズ全作品のプロデュースも行なう
―1作目『龍が如く』のキャッチコピーですね。
横山:僕も含めて当時のメンバーは20代中盤で、何をやって遊んでいたかというと、金曜日は蒲田(当時のセガ本社は大田区羽田)で朝まで飲んでいるわけですよ。だったらそれをそのままゲームにしようと、まずは繁華街を考えました。
東洋一の歓楽街といえば新宿・歌舞伎町。そこに生きている人々のドラマを生々しく描こうと思いました。小説であれば大沢在昌さんの『新宿鮫』があり、ゲームであれば刑事が主役のアドベンチャーゲームもあったので。
そのときにふと思い出したのがレンタルビデオ店のラインナップでした。そこにあるジャンルでゲーム化されてないものといえばVシネマ。コーナーとして成立するぐらいファンは多いけれど、ゲームにはなってない。これってじつはマーケティング的にも勝ち筋なんじゃないかとひらめいたんです。


「夜の街」の人たちの心をつかんだリアルな繁華街
―結果的にここまでシリーズが続いてきたわけですから、横山さんたちが設定したようなゲームに飢えている大人も潜在的にいたということなんですね。
横山:じつは発売当初は全然売れなくて、次第に流行り始めていきました。それも夜の街の人のあいだで。
―繁華街のリアリティにこだわったからこそでしょうか。
横山:そう、リアリティが一番大事でした。本当に繁華街に行った気になれるぐらいのものにしたかったんですよ。ただ、街の描写が大きく進化したのは『3』からでした。1作目のときは視点も完全に自由ではなく、画面を全体的に暗くするなどして細部が気にならないようにしていました。夜の場面が多いのは内容を踏まえると自然ですからね。
つまりハードスペックの関係で、緻密につくり込むには限界があるんです。視点を限定したり、見える部分を制限したりすることで、画面の処理落ちを避けていました。極端にいえば、立体風に見える平面の絵を貼っているだけ。それが『3』でハードが新しくなり、激的につくり方が変わった。視点も自由に動かせるから、今度はいかに街をつくり込むかという方向にシフトチェンジしていきました。
―なるほど。
ゲームは技術依存度の高いプロダクトですから、ハードとソフトの発展によって表現できる領域は必ず上がっていきます。でも、どんなに進化しても、やりたいと思うことには手が届かない場合があります。正直言えば、いまでも足りてない。処理落ち対策を必ずしなきゃ、ゲームは発売できないんですよ。


必要なリアリティと不必要なリアリティ
―具体的にはどんな部分が表現できていませんか?
横山:たとえば、細部の表現になりますが、眼鏡の描写。度数の強い眼鏡をかけると顔の輪郭はゆがんで見えますが、そこまでの表現はまだできていない。『7外伝』で主人公・桐生一馬は眼鏡をかけていますが、だて眼鏡になっています。
眼鏡越しの風景をゲーム内で表現しようとすれば、描画領域の異なる風景を2つ同時に処理しなければならず、泣く泣く断念しました。自分は目が悪いので、その妥協は気になっているんですけど……。
そういうふうにリアリティと一言でいっても、気になるポイントは人の数だけ変わるわけです。建築施工に詳しい人であれば、ビルの外観は精巧でも、エアコン室外機だったり換気扇の位置だったりがおかしければ、一発で違和感を持ってしまいます。


―メインストーリーの前日譚にあたる『0』は80年代が舞台ですよね。時代考証の監修者もチームにはいるのでしょうか?
横山:基本的に自分たちでやっています。だから自分たちで気づいていくしかない
―シリーズごとにやるべきこと、チェックすべきことは膨大にありそうですね。
横山:本当に大変ですよ。ただゲームはエンタメですから、娯楽性を削がないための嘘も必要だと思っています。たとえば時代劇でもあえて現代の言葉を使うことがありますよね。ストーリーを楽しんでもらうことが一番大事なので、どのリアリティを守り、どこで嘘をつくか。その見極めが重要です。
たとえば『8』の原子力開発から出た廃棄物の設定については設定考証をしっかりしています。そこで嘘をついてしまうと、リアリティが薄まってしまうから。低濃度廃棄物はこういったドラム缶に入っていて、運び出すときもこういう状態で……っていうのは丁寧にやりました。
一方で日本からハワイに行くまでの飛行時間をリアルに表現したら話が成立しなくなるので、そこは大胆に嘘をついています。

「龍が如く」がリアリティよりも大切にしていること
―ゲームはボタンを押すと話が進み、キャラクターを操作できて、ゲームの世界にプレイヤーが介入するようなインタラクティブな体験性を生み出せますよね。そういったゲームだからこそのリアリティを横山さんはどのように考えていますか?
横山:作品ごとにリアリティの定義は違うと思いますが、「龍が如く」に関していえば、リアルなものをつくりたいという欲望や発想はじつはないんです。
あくまでも「ゲームの空間にありそうなもの」が前提にあり、斬新なメインストーリーを楽しむことが軸。そこを大きく揺るがしてしまう要素でなければ、どんな非現実的なものでも盛ることができると思っています。


―メインストーリーが軸。それはかなり明確にあるんですね。
横山:明確です。よくメンバーには「『龍が如く』はカレーだよ」と言っています。メインストーリーはカレーのルーみたいなもので、そこにカツやチキン、福神漬けを乗せても、カレーのアイデンティティは失われない。
ちょっとカレーの話が続きますけど(笑)、カレーってルーの味が濃いから成立していると思うんです。多様なトッピングを中和して、あらゆるものをカレー味にしてくれる揺るぎなさがある。
「龍が如く」ではたくさんのミニゲームがあって、若いスタッフにミニゲームを採用するにあたってプレゼンしてもらっています。もちろんそれがつまらなかったら採用しませんが、設定や遊びの内容がどんなに突飛でも大丈夫。ルーのようにメインストーリーがそれを中和してくれるから。
―豊富なミニゲームには、そういう開発現場の秘密があったんですね。
横山:プロデュースやシナリオサイドにいる僕がやっているのは器づくりであって、そのなかの具は皆で決めているんです。グリーンピースが2〜3個入っていても味は変わらない。トータルのゲーム体験は「おいしいカレー食ったなあ!」ってなるので。


いちかばちかでシナリオに入れたVTuberのキャラクター
―今回の『8』を遊んでもっともグッと来たのが先ほど話された核廃棄物の問題や新興宗教を扱ったりする時事性です。またハワイが舞台ということもあり、行き場を失った男たちの物語が、間接的に移民の話にもなっている。そういう物語を選ぶことによって生じるリアリティが素晴らしかったです。
横山:そこはある種の賭けでした。1作目から『2』までの制作期間は実質的に8ヶ月くらいしかなかったので、物語にしても自分たちが見ている「いま」を扱えばよかったんです。でも『8』は完成させるまでに3〜4年かかったから、初期のシナリオづくりは未来予想みたいな仕事でした。
数年後の自分たちがリアルを感じられる世の中を考えなきゃいけなくて、今回でいえばVTuberの扱い方には不安もありました。彼らが3年後も流行していて、皆が知る言葉になっているかは未知数だったんです。
―流行が異常な速さで移り変わるのが現代ですからね。
横山:ゲームにおいて同時代的なリアリティを出せるか否かは、未来予想に近いと思います。1作目では神室町にミレニアムタワーという高層ビルが建つ、って話にしましたけど、歌舞伎町の中にも実際にビルが建っちゃいましたからね、しかも2つも。
ストーリー、架空のリアルを考えることは、世間が求めていることを考えることでもある気がします。だから、どこかのタイミングで現実と交差してくるんでしょうね。

テクノロジーが発達しても、重宝される人間の“能力”
―横山さんはシリーズ最初からシナリオを担当していますが、開発チームの存在も大きいのではないでしょうか?
横山:優秀なスタッフに恵まれたチームです。「龍が如く」は現代が舞台の作品なので、シリーズが続けば続くほど小道具や美術のアセットが増えていきます。ハードスペックがあまりにも変わると使えなくなりますが、『7』で登場した異人町やそのための道具はずっと使うことができる。
だから「7外伝」に至ってはキャラクター以外のほとんどのデータを流用してつくっていて、制作期間もわずか半年でした。でもそこで重要なのはデータの蓄積ではなく、人の蓄積。正確にいえば、個々人が持っているデータベースを検索する能力の蓄積です。
勤続年数が長いスタッフが多いで、シリーズのデータベース内に何が収められていて、それらを組み合わせればこういうものができるだろうとあたりをつける力に優れているんです。データベースの中身を知らない人だったら「いちからつくった方が早い」という考えになりがちですよね。
―AIや3Dスキャンのような先端技術があっても、それを使う人こそがやはり財産ということですね。
横山:創造というとゼロからものを生み出すことのように考えられがちですが、そういうものでもないと思うんですよ。たとえば昔の記憶を思い出した、なんて話がありますよね。その「思い出す」っていうのは人生や経験のハードディスクから特定のデータを見つけ出したってことなんだと思います。
これはゲーム制作も同じで、膨大なデータのなかからすぐに物を引き出せる検索能力こそが、クリエイティブで大事だと考えています。「龍が如く」チームは、その点で豊かで優れたスタッフが多いんじゃないかな。


AIに任せる仕事と人間に任せる仕事。そしてゲーム業界の今後
―人材の話をしたので、今度は技術面の話もうかがいたいです。たとえばAIは活用されていますか?
横山:龍が如くスタジオでは適材適所で使っています。簡単なところではゲームのデバッグはAIが担当しています。人間であるプレイヤーがいかにもやりそうなプレー、あるいはまずやらなそうなプレーを反復させて、突発的に出そうなバグをAIが24時間稼働で見つけるシステムを構築しています。人間が不得意な無機質な作業は、AIの得意とするところですね。
一方で、ゲームの感情的な部分にもAIを一部導入しつつあります。大きいところでは歓楽街のNPC(ノンプレイヤーキャラクターの略。プレイヤーが操作しないキャラなどを指す)の行動ですね。
昔の作品では、あらかじめ指定したコースをぐるぐる歩いているだけでしたが、街のリアリティを考えたら不自然ですよね。携帯を見たり、誰かを待っていたりする人もいる。そういう思考回路をNPCに実装するとリアルな街っぽくなるんです。

―近年は人のモーションや反応が抜群によくなっていた印象がありますが、それもAIでしょうか?
横山:そこはじつは人間の作業が関与しています。たとえばハワイを登場させるにあたって、NPCの骨格をすべて変えているんです。これまで日本人のキャラクターばかりをつくってきたので、ハワイの方についても開発初期はテクスチャーを変え、髪色を変更するなど海外の人のように見せていたんですけど、それだと違和感が出るんですよ。
考えてみれば、欧米の人の顔は日本人よりも小さいし、腰の位置も高い。骨格ごと変えなければハワイのリアリティは生まれませんでした。ハワイらしい建物とか有名なスポットを再現することも重要ですが、リアリティに関してもっと大切なのは、そういう見えづらい部分の細部の積み重ねです。

―最後にうかがいたいのは、これからのゲーム制作やその環境についてです。海外と比べて、日本発信のゲームが必ずしもスタンダードではなくなっているなかで、横山さんはどんな思いを抱いていますか?
横山:そこまで大きなことは考えないですね。ただ「龍が如く」というシリーズが始まって、世界中の人から「君たち、これいいね」と言ってもらえた。皆の期待に応えることも仕事の一部なのでつくり続けています。
とりとめのない話ですけど、未来のゴールはなくても、世界はこれからも思いもしない出来事がきっと起こってくるんですよね。天災もそうだし、技術発展もそう。そこを一つひとつ考えてもしょうがない。でも、時代の波に乗らなければいけないのは、ゲーム制作という仕事に関わる人間の運命で、サーフィンのように時代に乗って生き続けるんだと思います。

作品情報
-

『龍が如く8』
『龍が如く8』
『龍が如く8』は、どん底から再び這い上がる男「春日一番」と人生最期の戦いに挑む男「桐生一馬」の二人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いたドラマティックRPG。本作では、シリーズ初の海外ステージ・ハワイが登場。より戦略性を増した「新ライブコマンドRPGバトル」、豪華俳優陣が演じる魅力的なキャラクター、重厚なシナリオ、多彩なプレイスポットなどを楽しめる。
ゲストプロフィール
-
横山昌義(よこやままさよし)
横山昌義(よこやままさよし)
セガ「龍が如くスタジオ」代表・制作総指揮。セガ執行役員。1999年、セガにプランナーとして入社。「龍が如く」シリーズ初期作からシナリオ・演出を担当。2010年からシリーズ全作品のプロデュースも行なう。
Co-created by
-
島貫泰介
ライター
島貫泰介
ライター
美術ライター / 編集者。1980年神奈川生まれ。京都・別府在住。『Tokyo Art Beat』『CINRA.NET』『美術手帖』などで執筆・編集・企画を行う。2019年には三枝愛(美術家)、捩子ぴじん(ダンサー)とコレクティブリサーチグループを結成。2021年よりチーム名を「禹歩」に変え、展示、上演、エディトリアルなど、多様なかたちでのリサーチとアウトプットを継続している。
- かもべり | ソーシャルディスタンスアートマガジン: http://kamoberi.com/
-
タケシタトモヒロ
フォトグラファー
Tag
Share
Discussion
Index
Index
Archives
Recommend
Recommend
Recommend
Recommend
Recommend
-

{ Special }
シニア世代も念頭にインクルーシブなミラーワールドを
シニア世代も念頭にインクルーシブなミラーワールドを
シニア世代も念頭にインクルーシブなミラーワールドを
-

{ Community }
デザインリサーチャー・清水淳子が選ぶ、10年後の未来を予測するためのインフォメーションデザイン5選
デザインリサーチャー・清水淳子が選ぶ、10年後の未来を予測するためのインフォメーションデザイン5選
デザインリサーチャー・清水淳子が選ぶ、10年後の未来を予測するためのインフォメーションデザイン5選
-

{ Community }
「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像
「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像
「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像
-

{ Community }
メタバースデザイン
メタバースデザイン
メタバースデザイン
Hot topics
Hot topics
Hot topics
Hot topics
Hot topics
-

{ Community }
香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来
香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来
香りは記憶を超え、行動を変える。セントマーケティングのプロ・浜田剛知が語る、デジタル×嗅覚の未来
-

{ Community }
安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性
安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性
安藤忠雄設計のトイレが舞台に。GEMINIが切り開くメディアミックスの可能性
-

{ Community }
歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光
歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光
歴史のなかで「いま」という瞬間を伝える:カタルーニャのアーティスト、シャビ・ボベが表現する光
-

{ Community }
聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?
聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?
聖地巡礼の新たなかたち。セマーン・ペトラが映すフィクションと現実の境界とは?
-

{ Community }
XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現
XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現
XR映画とは何か?『Beyond the Frame Festival』で体験する未来の映像表現
-

{ Community }
エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法
エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法
エシカルファッションとは?注目すべき3ブランドと、サステナブルなスタイルの実践方法
-

{ Community }
「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像
「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像
「デジタルファッション元年」の到来。アンリアレイジが見る洋服の変化と次なるデザイナー像
Special
Special
Special
Special
Special
Featured articles spun from unique perspectives.
What Is
“mirror world”...
What Is
“mirror world”...
What Is
“mirror world”...
What Is
“mirror world”...
What Is
“mirror world”...
“mirror world”... What Is
“mirror world”... What Is
“mirror world”... What Is
“mirror world”... What Is
“mirror world”...
PROJECT GEMINIとは?
TOPPANが提唱するミラーワールドの形。
Go Down
Go Down
Go Down
Go Down
Go Down
The Rabbit
The Rabbit
The Rabbit
The Rabbit
The Rabbit
Hole!
Hole!
Hole!
Hole!
Hole!
不思議の国へようこそ!あなたもPROJECT GEMINIに参加しませんか?